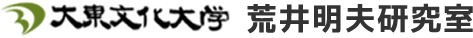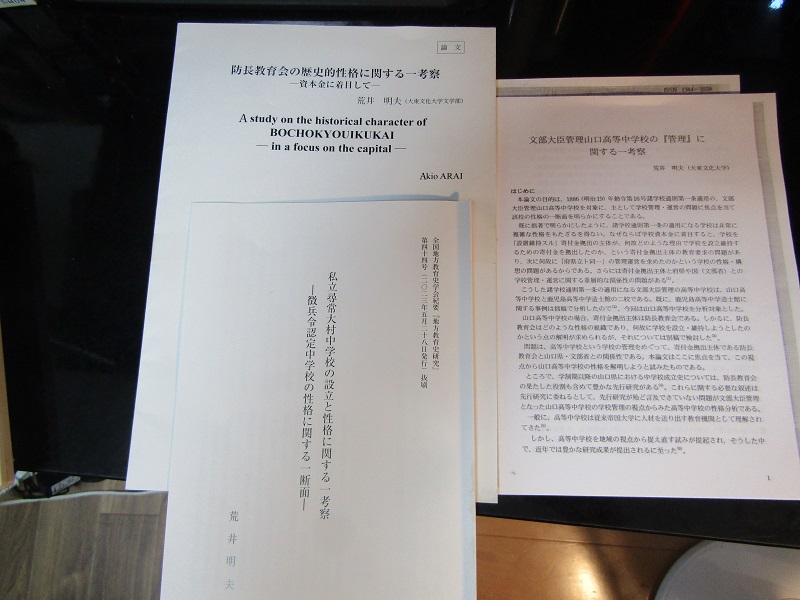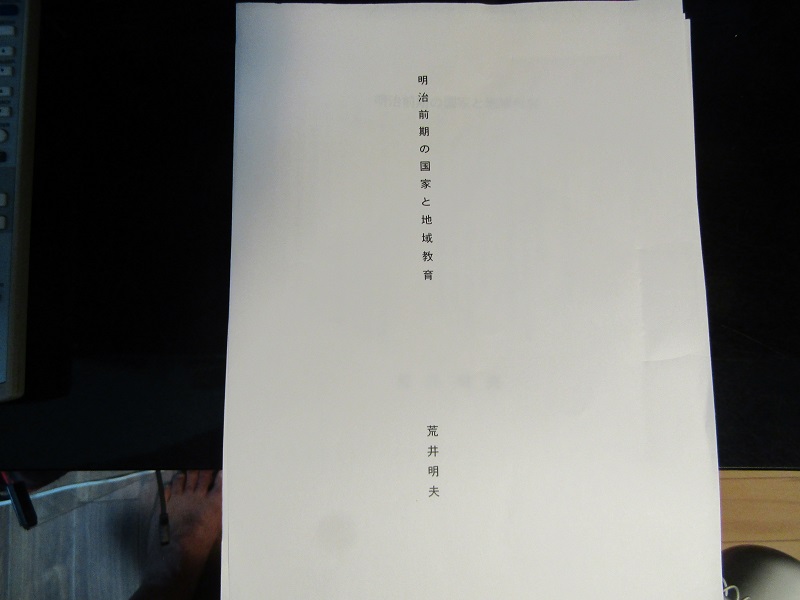2024年04月16日
前にも報告しましたが、私の単著2冊目となる『明治前期の国家と地域教育』の、出版社に渡す原稿をまとめる作業を8月にやっていましたが、それ以降の9月からの報告です。
まず、この『明治前期の国家と地域教育』の刊行助成を受けるべく、大学の特別研究費(刊行助成)と、日本学術振興会の「研究成果公開促進費」に応募する書類作成に追われました。8~9月の最重要の課題でした。年明けの1月には大学から、4月には日本学術振興会から、それぞれ採択されたという連絡を頂きました。
それを受けて、2月以降は、「索引づくり」と徹底した読み込みによる「誤植のチェック」でした。400ページを越える大著になりましたのでチェックが大変でした。でもなんとかそれも終えました。出版社である吉川弘文館から、本格的な作業に入ったという連絡を受けました。あとは校正です。
それと2024年度に申請した基盤研究Bも採択され、,予算を付けて頂きました。テーマは「明治前期における地域の中等教育要求の組織化に関する研究」です。徴兵令認定中学校の研究に力をいれていきたいと考えています。また報告します。