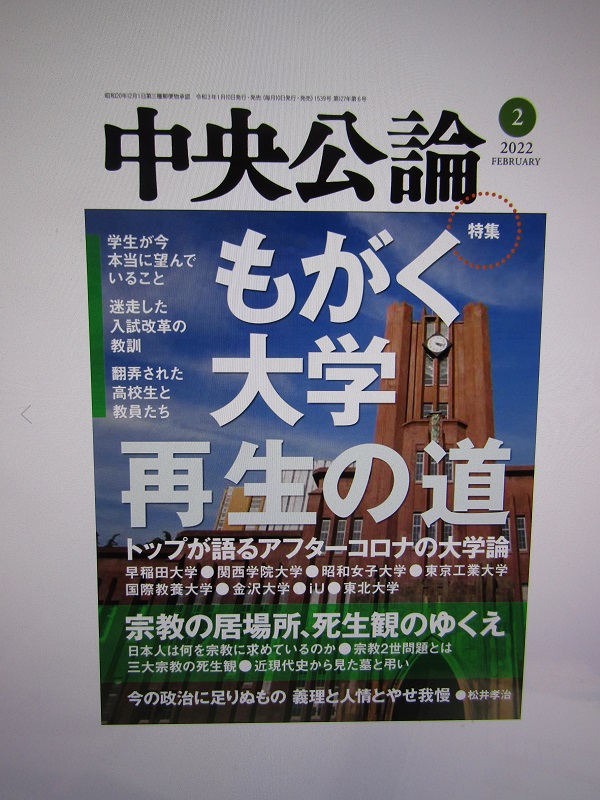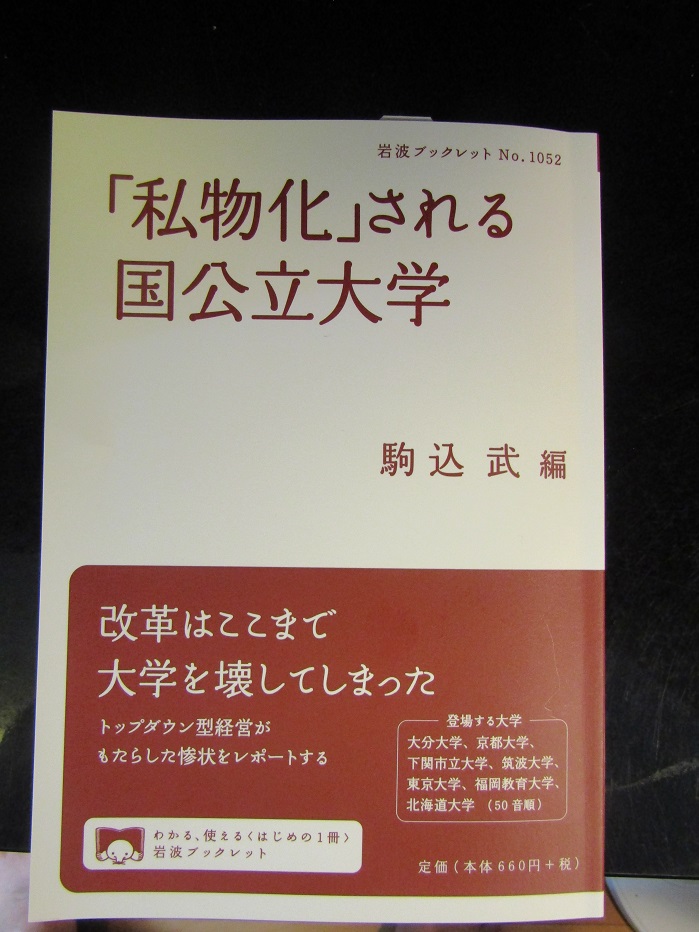2024年07月06日
久しぶりの読書日記です。私の読書の方法ですが、一時に数冊の本を読みます。一週間で4~5冊を読みますが、年間で平均約200冊を読んでいます。今週の読書日記です。
まず通勤の車中です。読み易い本を持参しそれを読みます。少し時間に余裕を持ち、なるべく座って通勤できるようにしています。文庫・新書・軽い読み物、が中心です。講義のネタ本やゼミのテキストは持ち込みません。今週は、各新聞紙の「読書コーナー」でベストテン入リした『成瀬は天下を取りにいく』『なぜ働いていると本がよめなくなるのか』『シャーロックホームズ最後の挨拶』の3冊をよみました。『成瀬・・』はちょっと変わった、でもしっかり者の女子高校生が主人公の青春物語。『何故・・』は、どうしてどうしてタイトルとは異なってちゃんとした近代日本社会史(教養・思想史)になっています。読者に注目した読みごたえあるものでした。『ホームズ』は私の小学生以来の愛読書です。
一日の中の、一定の空き時間、またはその日の仕事が一段落した後にはハードなもの、またはデキスト・講義関係書物、専門書、を読みます。
法政大学総長だった田中優子先生の『言葉は選ぶためにある』は珠玉のエッセイでした。
石牟礼道子『苦海浄土』はじめ渡辺京二先生の名著などもふんだんに取り入れられて夢中になります。暉峻淑子先生の『承認をひらく』も、人権や民主主義の危機的状況下にあって現代社会に向き合う視点を「承認」というキーワードから解明しているものでした。読みごたえある内容です。先生には『豊かさとは何か』という名著がありますが、それに匹敵する内容です。私事になりますが、埼玉大学時代、先生の「生活経済学」は本当に刺激的な講義でした。大学に入って初めて「面白い」と実感した講義でした。
夜寝床で読む本は、専ら音楽関係です。飯田昭夫さんの『フルトヴェングラーの地平』は、多様な指揮者・音楽家を20世紀最大の指揮者フルトヴェングラーを中心において俯瞰した内容となっています。
大凡一週間から10日程度で読みました。週末になると次に何を読むか、計画を立てるのが楽しみです。